市民法務等、実直に支援します
Administrative Lawyer
WATANABE office
マンション管理業務MANSION ADMINISTR-ATION
マンション管理・運営等、総合的な支援
当事務所のマンション管理士,宅地建物取引士,管理業務主任者の業務について、掲載しています。
![]()
マンションの資産価値や立地環境、建物・設備の構造精査など、購入時に立会い・見学会同行、契約時の同席など、適正で安心ある購入を「マンション管理士」として、サポートしています。また、売却での相談や価格帯への精査、専有部分のリフォーム施工、宅建業者との折衝など、売却時の不安解消に向けて、マンション全般を「宅地建物取引士」として取引等を総合的にサポートしています。
基本「報酬額表」はこちら。
マンションを「長持ち」させる専門的な経験則と「物を大切にする和人の精神性」で支援
建物・設備・複合施設などの適正な維持を考え、適度な小修繕・計画的な大規模修繕、耐震改善・対策、防災・防犯提案を行います。マンションは、区分所有者の大切な資産です、最適な維持・管理について、専門家として適正化を真剣にお手伝いしています。
コミニティ形成への取組みを全面的にサポート
区分所有者・管理組合・理事会・各種委員会等の会合に参加して、マンションの維持・管理・諸問題の予防/解決策、防災対策、修繕計画などの解説(助言等のアドバイス)・ガイドも行っています。
報酬額の目安は、1時間¥2,500です。 管理組合(専門部会等)への支援として、「マンション勉強会」も実施しています。お気軽にお問合せ下さい。
管理規約、使用細則、駐車場細則、管理組合会計細則など、改定・制定への支援
マンションには共同生活の居住形態として、権利・利用関係の区分所有法での法定事項や管理規約等の諸ルールを守る必要があります。マンションの権利関係・居住ルールを定めた「管理規約」や「使用細則」「駐車場細則」など、最新法令と生活体制に合わせた作成・改定・制定等を含めて、マンション内のルール作りを行います。この作業は、マンション管理士の重要な業務となっています。 居住での法的な相談から、福祉・介護、生活での諸問題、管理会社・他業者とのトラブル、折衝にも、専門家として改善に関わっています。また、「介護福祉士」の有資格者が、マンションに居住しているご本人様・ごの家族のご意向やご希望に配慮して、福祉・介護・障がい者相談にも実直に取り組んでいます。
管理組合・理事会・各種専門部会への支援(外部専門家・理事長/理事/監事への就任含む)
マンションの生活には、管理組合が主体として機能していることが大切です。管理組合・理事会・各委員会・総会等の運営をアドバイザーとして、支援しています。また、年間を通じての補佐役として、顧問を受任し、『顧問マンション管理士』としてもお手伝いしております。また、管理組合の運営全般(管理・維持・保全・防犯防災・官公署や関連業者との連携など)の執行責任を担っている理事長、理事、監事への就任を受託して、第三者管理者・外部専門家として、管理全般の適正化をサポート。
〔外部専門家の活用ガイドライン(国土交通省ホームページ公表)〕
管理組合・理事会・専門部会等への関わり
マンションの生活には、管理組合が主体として機能していることが大切です。管理組合・理事会・各委員会・総会等の運営をアドバイザーとして、支援しています。また、年間を通じての補佐役として、『顧問・アドバイザー』もお受けしています。メリットとして、法令改正の最新情報や修繕等の業者折衝、管理・会計面の精査、理事会・総会への同席、居住者間のトラブル予防と解決などが顧問料金のみで可能となります。
【マンション内の居住者間トラブル解決へのお手伝い】
マンション内の住民間でのトラブルは、居住生活での居心地に直結します。コミュニティ形成をお手伝いして、居住者間の関係緩和やトラブル予防と解決に取組みます。合意形成や意思決定に向けた体制作りなど、区分所有者間及び管理会社との円滑な管理組合運営・維持を、真摯に、丁寧に、真剣に、改善を提案します。尚、現状の管理会社からの変更等、新たに管理会社を選定する際にも、管理会社との関係構築及び管理組合内の合意形成を、丁寧にサポートします。
【マンションの管理費等の適正化へのお手伝い】
区分所有者が負担している「管理費」「修繕積立金」「駐車場使用料」などの未払い問題を含め、収支内容の会計を診断・精査して、適正化を進めます。尚、収支決算書作成と監査(年間収支)行います。(※監査を実施した際は、「監査報告書」を作成し、マンション管理士として記名・職印を施しますので、一定の信用度が付与されます)。
『未払い問題:滞納者対応』について:
公益財団法人マンション管理センター(マンションの適正化を国交省より移管されている機関)が発行し、指針としている「滞納者管理費等に関する法的対応指針」に則り、適正化を構築するべく、滞納者への徴収業務を進めていきます。マンション管理組合の債権(一般の共益費的な法解釈がされており、水道や電気等の光熱費同様に民法にて先取特権として位置付けされています)として、滞納者に対して、管理組合と組合員(滞納者)との契約上(根拠は管理規約等)の権利として、滞納改善を遂行します。具体的には、滞納者への督促文の送付にて滞納改善を促し、改善がない場合は、法的な手続に移行することとなります。滞納者への督促は、管理規約上の条文が根拠ですので、この部分に不備がある場合は、管理規約の一部改定等が必要になります。督促業務がどこまで可能なのか? 専門家として適切なアドバイスや規約作成・改定にも関わります。(マンション管理士は、規約作成・改定・制定の専門家です)

「管理規約等」の作成・改定への手続きについて
管理規約は、マンションの根本ルールです。法的に例えると憲法に位置付けられます。現行規約が古く、現在の法令が反映されていない場合や居住形態などの変更(ペットの飼育、管理体制を第三者管理に切り替えるなど)等で、規約や細則の変更が必要な場合等、規約改定には様々な背景と諸事情があります。
マンション管理士は、規約作成・修正、改定・策定、合意形成まで、トータルに関わる専門家です。当事務所の専門性として、最も得意としている領域でもあります。
【規約改定への手続と流れ】
1. 現に使用している規約について、条文ごとに精査しつつ、変更の諸事情を整理します。
![]()
2. 法定されている「標準管理規約」を基準に、作成素案(対照表含)を提示します。(改定案を決議日の14日前に総組合員へ事前配布する)
![]()
3.「新規約案」への最終判断を管理組合総会等で合意形成を行い、効力のある規約と位置 付けます。規約の制定・改廃(変更・廃止)は、総組合員による区分所有者(人数)及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議(特別決議)によって行います(区分所有法31条)。*成立するには総組合員の各4分の3以上(75%)の賛成が必要となりますので、決議当日、欠席された分は委任状にて合計数を算出します。尚、反対する場合にも一定の決まり事があります。それは、事前に反対の意思を管理組合の管理者(理事長)へ通知するというルールです。これは当日に反対することで議場が混乱することを防止する方法として、団体等の決議に取り入れられているルールです。
また、規約の設定、改廃が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その承諾が必要となります。これらは強行法規であることから、不可欠な手続きとなります。この特別の影響とは、区分所有者全員が受ける利益と比較して、一部の区分所有者が受ける不利益が我慢すべき限度(受忍限度)を超えるのかが、判断基準とされています。例えば、共用部分の管理は規約で別段の定め(理事会が利用・改良行為を決定するなど)が可能ですが、その行為が専有部分の使用に特別の影響を及ぼす場合は、その所有者の承諾を得るなどです。
![]()
4.「規約原本」を証するため、区分所有者全員が署名押印(又は電磁的記録に電子署名)した規約を一通作成し、規約原本として管理組合の理事長が保管します。(理事長には関係人からの閲覧へ、対応
する義務が生じます)
![]()
5.規約条文の末尾(附則)に、マンション管理組合理事(理事長)様より、ご依頼を受けた代理人として、マンション管理士として、記名押印(管理士登録番号)(職印)を施します。マンションの専門家が法令等に則り作成/編集・改定した証となります。
マンションの維持保全/修繕について
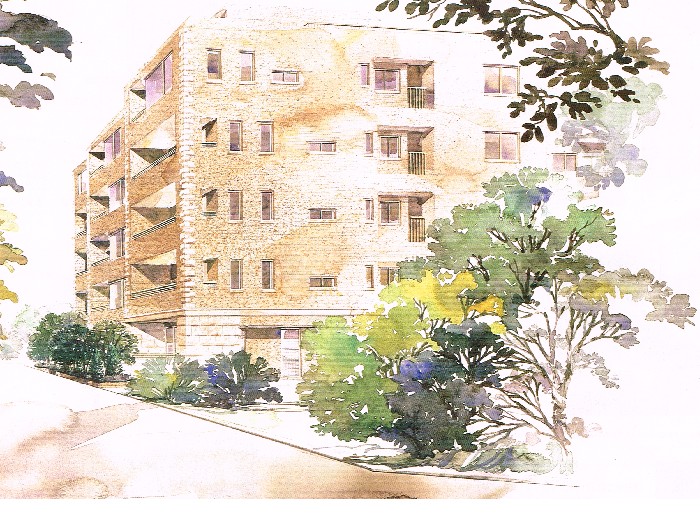
管理の適正化指針:
管理組合は、「マンション管理適正化指針に定めるところに留意して、マンションを適正に管理するように努めねければならない」と規定され、指針には、マンションを長く使えるように維持していくために、『保守点検』や『定期的な修繕』を計画的に実施することが示されています。マンションは、居住者の単なる個人的な資産形成の問題にとどまらず、その地域における社会的資産の面も有しています。これらの資産の維持・管理について、管理組合が責任を持って管理するのは言うまでもありませんが、国や地方公共団体においても積極的に支援するように規定されています。
マンションの居住性や資産価値を低下させずに、快適なマンションライフを送れるように、維持・保全を行う必要があります。
保守点検について:
保守点検とは、建物の機能を維持するために、建物各部の不具合や設備機器等の作動環境に異常がないかどうかを定期的に検査し、消耗品の交換や作動調整、日常的な補修(経常的な修繕)を行うことをいいます。マンション管理の現場では最初に行う「目視点検」(肉眼で点検すること)、その点検から不具合や異常等を発見した場合の、その場での微調整や消耗品を交換する行動は、点検行為と位置付けられます。会計区分として、日常的な経常修繕は、月々の管理費(保全費用)から支払いします。日常的な経常修繕と区別されるのが、、修繕工事となります。修繕工事は、特別管理として、修繕積立金から拠出されます。
尚、保守点検には、法令で定められている「法定点検」と、管理組合が任意に行う「自主点検」があります。
修繕とは:
修繕とは、建物部材の劣化、設備の故障などについて、修理や取替を行う行為で、建物又は設備の使用上、支障のないようにすることです。要するに、それらの機能を建設当初のレベルまで回復させることを目的として行います。また、修繕には、故障や機能低下などに、その都度、対応する「小修繕」と、一定年数の経過ごとに行う「計画修繕(大修繕)」とに分かれます。
建築基準法 第2条14号での「大規模修繕」とは、「建物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕」と定義されています。
例えば、一種類の主要構造部(屋上・屋根など)を修繕する場合でも、その修繕箇所が主要構造部の過半に及ぶ場合は、大規模修繕工事となります。但し、一概に定義することが現実にそぐわないこともありますので、維持・保全面を含めて、一般的には10年に1度程度、実施する大掛かりな工事が「大規模修繕工事」とされています。
「マンション標準管理規約」では、長期修繕計画の作成が規程されています。要約すると以下の内容となります。
①建物を長期にわたって良好に維持・管理していくためには、一定の年数の経過ごとに計画的に修繕を行っていくことが必要であり、「その対象となる建物の部分」、「修繕時期」、「必要となる費用」等について、予め長期修繕計画を定め、区分所有者の間で合意しておくことは、円滑な修繕の実施のために重要であること。
②長期修繕計画の内容として以下が最低限必要である。
(1)計画期間が25年程度以上であること。新築時は30年程度。修繕のために必要な工事をほぼ網羅できること。
(2)計画修繕の対象となる工事として、「外壁補修」「屋上防水」「給排水管取替え」「窓及び玄関扉等の開口部の改良等」が含まれ、各部位別の修繕周期、工事金額等が定められたものであること。
(3)全体の工事金額が定められたものであること。また、定期的な(おおむね5年程度)の見直しが必要であること。
③「長期修繕計画」の作成又は変更、修繕工事の実施の前提として、劣化診断(建物診断)を管理組合として、併せて行う必要があること。
長期修繕計画と修繕積立金:
修繕積立金は将来の小規模・大規模修繕工事等に対応するために積み立てられるものです。当然ながら、いざ、工事が必要となった際、足りない状態では修繕工事が出来ずに、建物への劣化を深刻化される事態へと繋がります。
このような事態とならないために、各組合員が月々納める「修繕積立金」は、長期修繕計画等から逆算されて導き出すことが肝要となります。要するに、修繕計画があるからこそ、修繕積立金が設定され、各組合員より月々納めて頂く必要があり、根拠としての意味合いともなっています。
「長期修繕計画作成ガイドライン」(国土交通省)において、次のとおり示されています。
〔推定修繕工事費の算定〕
一 数量計算の方法
数量計算は、新築マンションの場合、設計図書、工事請負契約による請負代金内訳書、数量計算書等を参考とし、また、既存マンションの場合、現状の長期修繕計画を踏まえ、保管している設計図書、数量計算書、修繕等の履歴、現状の調査・診断の結果等を参考とし、「建築数量積算基準((財)建築コスト管理システム研究所発行)」等に準拠して、長期修繕計画用に算出します。
二 単価の設定の考え方
単価は、修繕工事特有の施工条件等を考慮し、部位ごとに仕様を選択して、新築マンションの場合、設計図書、工事請負契約による請負代金内訳書等を参考として、また、既存マンションの場合、過去の計画修繕工事の契約実績、その調査データ、刊行物の単価、専門工事業者の見積価格等を参考として設定します。
なお、現場管理費及び一般管理費は、見込まれる推定修繕工事ごとの総額に応じた比率の額を単価に含めて設定します。
三 算定の方法
推定修繕工事費は、推定修繕工事項目の詳細な項目ごとに、算出した数量に設定した単価を乗じて算定します。
修繕積立金の運用益、借入金の金利及び物価変動について考慮する場合は、作成時点において想定する率を明示します。また、消費税は、作成時点の税率とし、会計年度ごとに計上します。
推定修繕工事費は、推定修繕工事項目(小項目)ごと又は部位ごとに仕様を設定し、算出した数量に設定した単価を乗じて算定します。この内訳書を基に修繕周期に沿って年度ごとに必要な推定修繕工事費を整理して表にまとめます。
〔収支計画の検討〕
計画期間に見込まれる推定修繕工事費(借入金がある場合はその償還金を含む。以下同じ。)の累計額が示され、その額を修繕積立金(修繕積立基金、一時金、専用庭等の専用使用料及び駐車場等の使用料からの繰入れ並びに修繕積立金の運用益を含む。以下同じ。)の累計額が下回らないように計画することが必要です。
また、推定修繕工事項目に建物及び設備の性能向上を図る改修工事を設定する場合は、これに要する費用を含めた収支計画とすることが必要です。
なお、機械式駐車場があり、維持管理に多額の費用を要することが想定される場合は、管理費会計及び修繕積立金会計とは区分して駐車場使用料会計を設けることが望まれます。
収支計画は、計画期間中に必要な推定修繕工事費等の累計額と修繕積立金等の累計額の関係が把握できるように示されていることが必要です。したがって、計画期間の終期において、推定修繕工事費等の計画期間の累計額を修繕積立金等の計画期間の累計額が下回らないように収支計画をたて、グラフで分かりやすく示します。
なお、建物や設備の性能向上を図る改修工事を設定した場合は、これに要する費用を含めた収支計画とします。
〔収入の考え方〕
区分所有者が積み立てる修繕積立金のほか、専用庭等の専用使用料及び駐車場等の使用料からそれらの管理に要する費用に充当した残金を、修繕積立金会計に繰り入れます。
また、購入時に将来の計画修繕工事に要する経費として修繕積立基金を負担する場合又は修繕積立金の総額の不足などから一時金を負担する場合は、これらを修繕積立金会計に繰り入れます。
修繕積立金会計は管理費会計と区分して設けます。
修繕積立金会計の計画期間の収入としては、(計画の見直しの場合は修繕積立金の残高のほか)
①修繕積立金、②専用庭等の専用使用料や駐車場等の使用料などからの繰入れ金、③修繕積立金の運用益などがあります。また、④分譲時に修繕積立基金を負担する場合や⑤修繕積立金の総額の不足などから一時金を負担する場合はこれらを含めます。
尚、計画期間の支出としては、①推定修繕工事費の累計額のほか、②借入金がある場合は、計画期間の償還金(元本と利息)を含めます。
〔長期修繕計画の見直し〕
長期修繕計画は、次に掲げる不確定な事項を含んでいますので、5年程度ごとに調査・診断を行い、その結果に基づいて見直すことが必要です。また、併せて修繕積立金の額も見直します。
①建物及び設備の劣化の状況
②社会的環境及び生活様式の変化
③新たな材料、工法等の開発及びそれによる修繕周期、単価等の変動
④修繕積立金の運用益、借入金の金利、物価、消費税率等の変動
長期修繕計画の内容は、作成時点での25年~30年程度の劣化の予測に基づくものです。経年とともにその状況が変化していくこともあり、予測と実態のズレが生じます。したがって、適切かつ効果的な修繕工事を行うためには、5年程度ごとに、建物及び設備の調査・診断を行って、劣化状態、組合員の要望などを把握し、十分な検討を行ったうえで、長期修繕計画を見直すことが必要です。
見直しのポイントは次のとおりです。
① 調査・診断を行い、修繕履歴や建物・設備の劣化状況などに応じて、推定修繕工事項目の内容や修繕周期を見直す。
② 経済的な変動、新技術の開発等を考慮して、推定修繕工事費や収支計画を見直す。
③ 建物や設備の性能向上工事を計画に盛り込むことを検討する。
*計画の検討段階から区分所有者側の第三者的なアドバイザーとして、マンション管理士、管理業務主任者等の専門家を加えることをお勧めします。
ワタナベ総合法務事務所
〒030-0812
青森県青森市堤町1-3-14
TEL 017-765-6363
FAX 017-765-6364